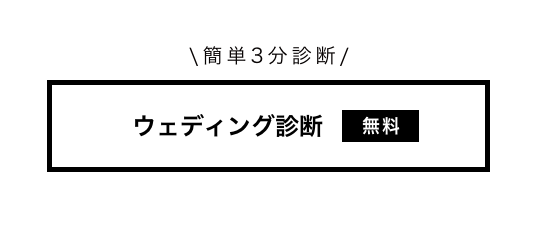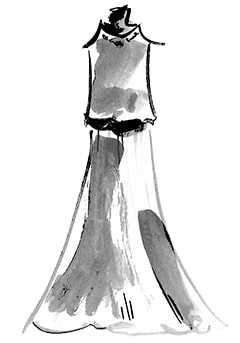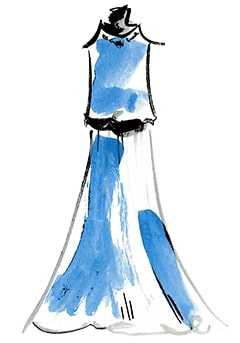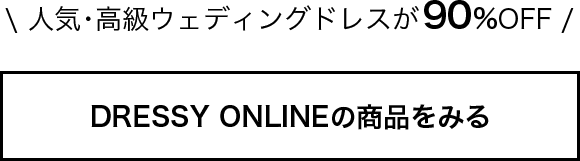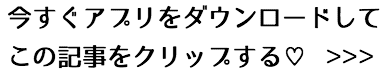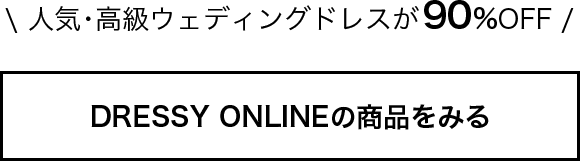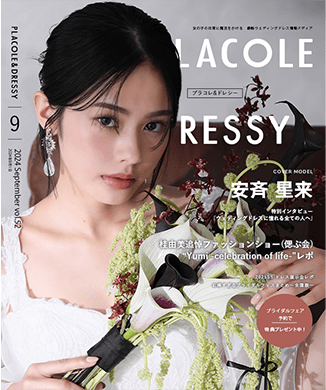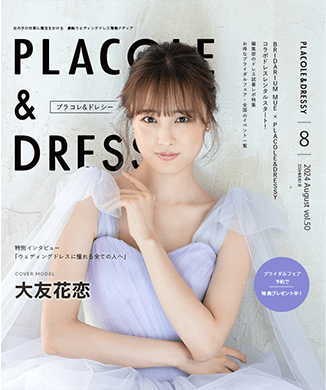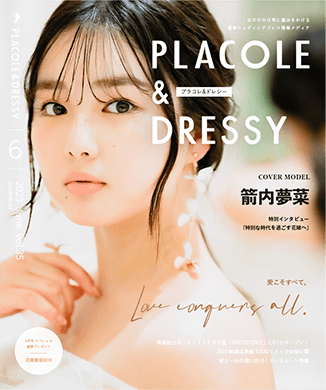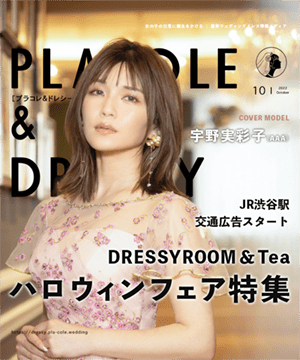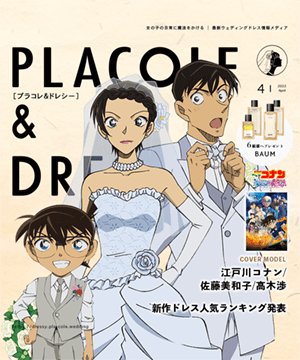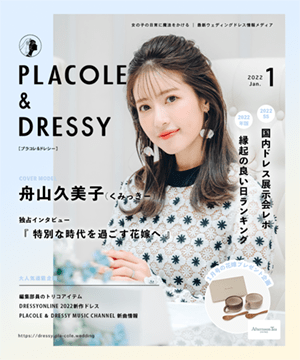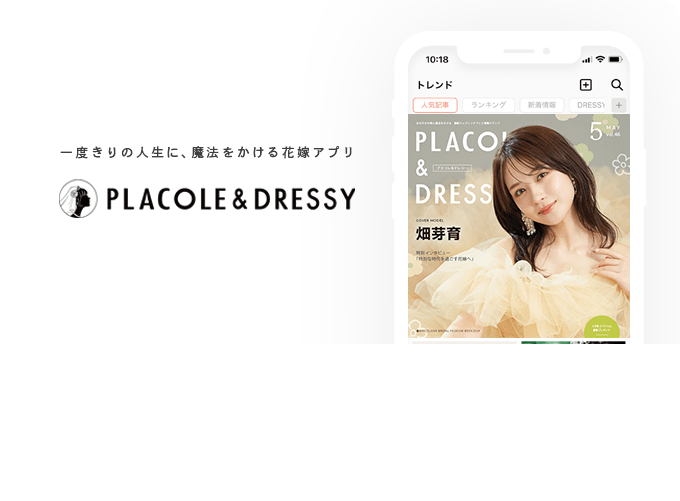出生前診断について

では続いて、着床前診断と一緒くたにされがちな出生前診断についても詳しくご紹介します。そもそも出生前診断とは、妊娠中の胎児の状態や疾患の有無について調べる検査のことを言います。
出生前に胎児の状態を知っておくことで、最適な分娩方法や療育環境を用意することを目的に行われるこちらの検査ですが、近年では出生前にダウン症などに疾患が無いか調べるために検査を受けるカップルも増えています。
出生前診断種類

出生前診断には、非確定的検査(非侵襲的検査)と確定検査(侵襲的検査)の二種類があり、一般的に非確定的検査の方が母体への負担が少なく、流産リスクがない検査だと言われています。こちらはあくまで赤ちゃんの疾患の可能性を評価する検査となるので、もし検査の結果染色体異常が見られた場合は別途検査を受ける必要があります。
一方で確定検査は疾患の診断を確定させるために行う検査のことを言います。検査内容には羊水検査や絨毛検査などがあり、母体への負担が大きく、流産のリスクが伴います。
出生前診断を受ける人の割合

出生前診断の受診率は母体の年齢により異なります。具体的には以下をご参照くださいませ◎
●母体の年齢が35歳以上:35%
●母体の年齢が40歳以上:60%
この背景には、ダウン症の子どもを妊娠する確率が大きく影響しています。母体の年齢が40歳を超えるとダウン症の子どもを妊娠する確率は100分の1の割合となっており、他人事ではありません。
母体の年齢が40歳を過ぎるとこういったリスクも高まることから事前に出生前診断を受ける方の割合も増加することが伺えます。
出生前診断陽性者の中絶率

また実際に出生前診断を受け、陽性判定を受けた方の中絶率は世界規模で見てもおおよそ90%だと言われています。この結果からも分かる通り、出産前に自分の子どもに重度の障害があることが分かると、ほとんどのカップルが残念ながら中絶という道を選んでいます。
一部では命の選別だとも言われている出生前診断。受ける・受けないは本人次第ですが、受けることそのものに悩む女性も少なくはないそうです。
着床前診断と出生前診断の違いについて◎