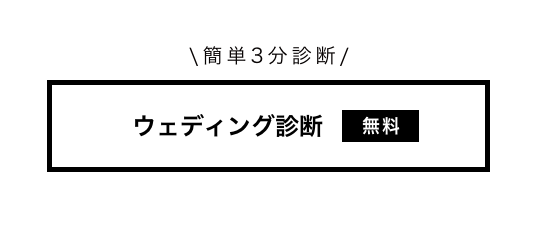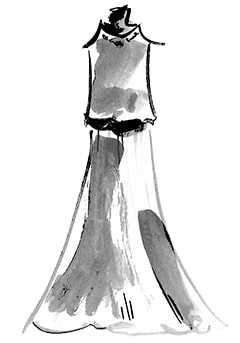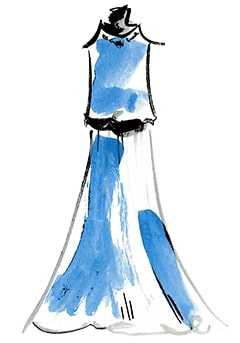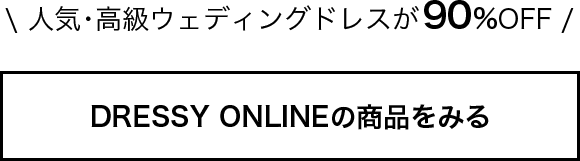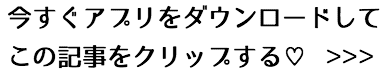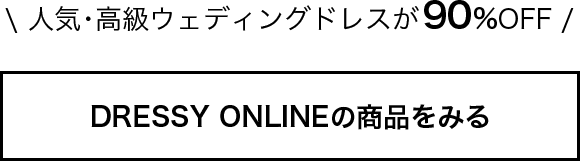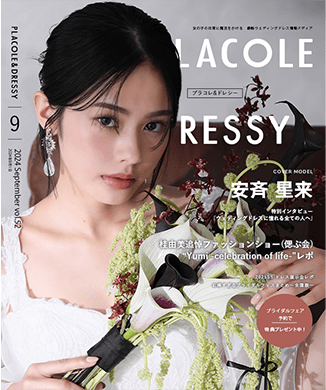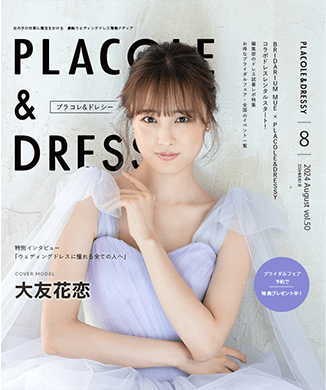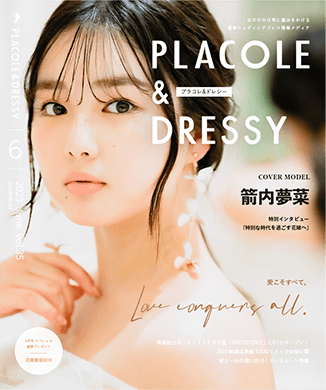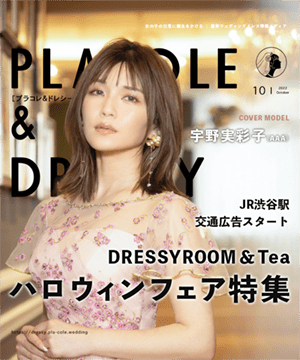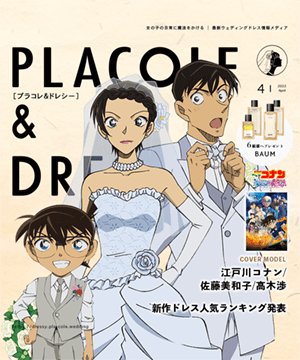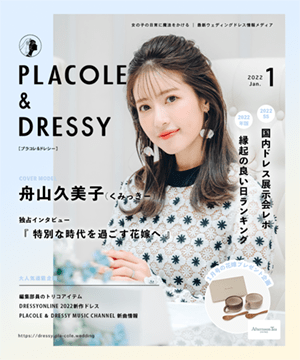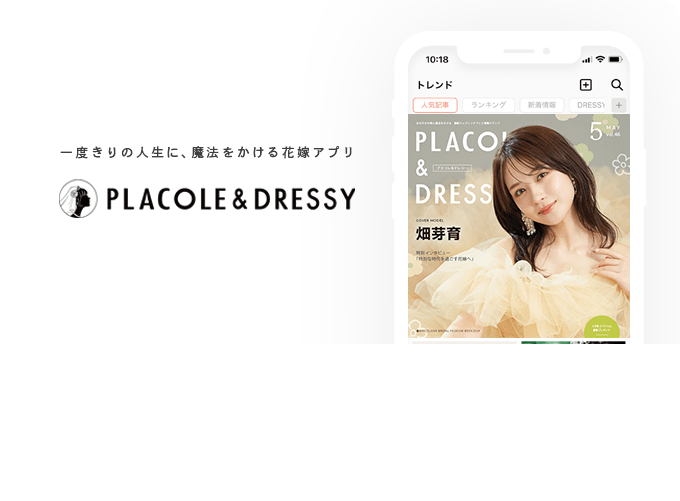六曜の一つである「先負」。聞いたことがあっても、意味まで詳しく知っている方は意外と少ないかもしれません◎
そこで本日は先負の基本的な情報をご紹介します。先負の意味をはじめ、歴史や由来、現代における先負の活用方法など、幅広くご紹介するので、ぜひ最後までご覧くださいね!
先負(せんぶ)とは?六曜の中での意味と位置づけ

六曜の一つに数えられる先負。一般的な読み方は「せんぶ」ですが、場合によっては「さきまけ」「せんぷ」などと読まれることもあります。「先んずれば負ける」という意味を持ち、午前は凶、午後は吉とされ、時間帯によって吉凶が変わる日です。
六曜は冠婚葬祭や重要な予定を立てる際の目安として古くから用いられてきました。先負の日は、焦って行動するのは避けるべきとされ、もし何か始めるのであれば午後の時間帯を選ぶのが良いとされています◎
六曜の基本知識
そもそも六曜とは、暦の中で日ごとの運勢や吉凶を示す指標のことを言います。先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つから成り、各日の行動に影響を与えるものとされています。
日本では、特に結婚式や引越し、開業などのタイミングを六曜に合わせる風習が根付いています。「験を担ぐ」という意味でも特別な日を迎えるにあたり、六曜を気にする人が多い傾向があります。
先負の⽇の特徴と運勢の流れを解説
「先んずれば負ける」という意味を持つ先負。この日は急いで物事を進めたり、先手を打つのは避け、慎重に物事を進めるべき日とされています。特に勝負事や契約など、先手を打つことが重要とされる場面では注意が必要です。
午前は凶・午後は吉とされている日なので、もし何か行動を起こすのであれば、午後の時間帯をおすすめします。先負の日は無理に行動を起こすのではなく、あえてゆったりと静かに過ごすのもおすすめです。
先負の由来と歴史