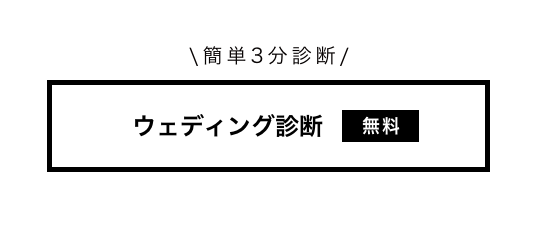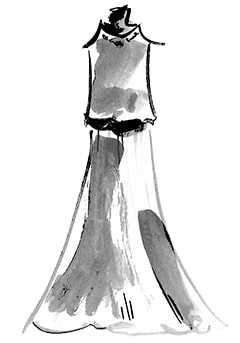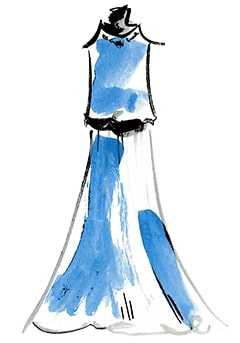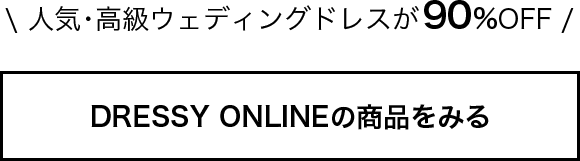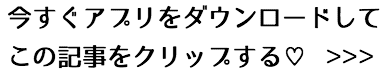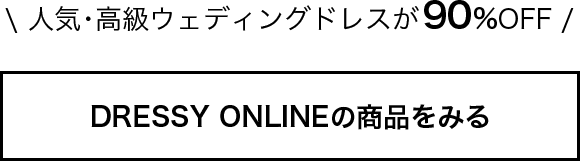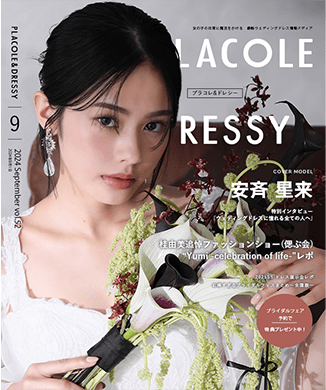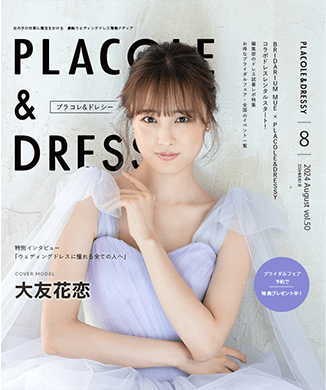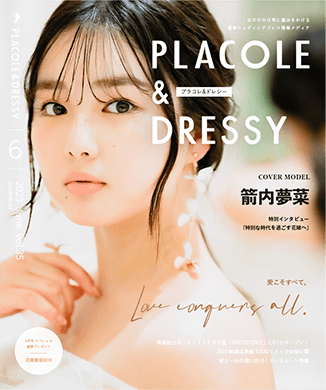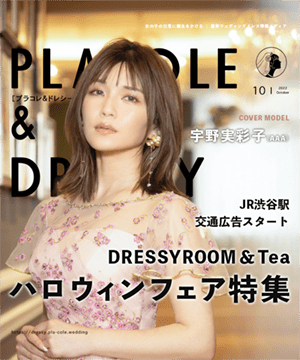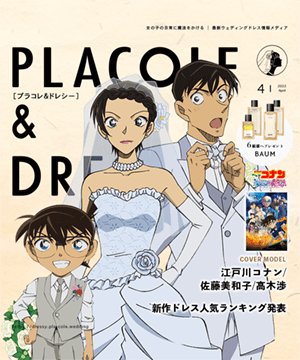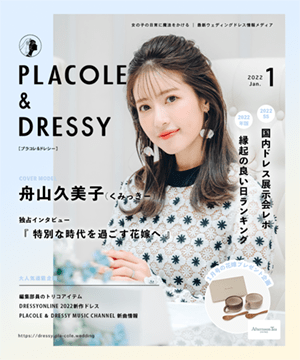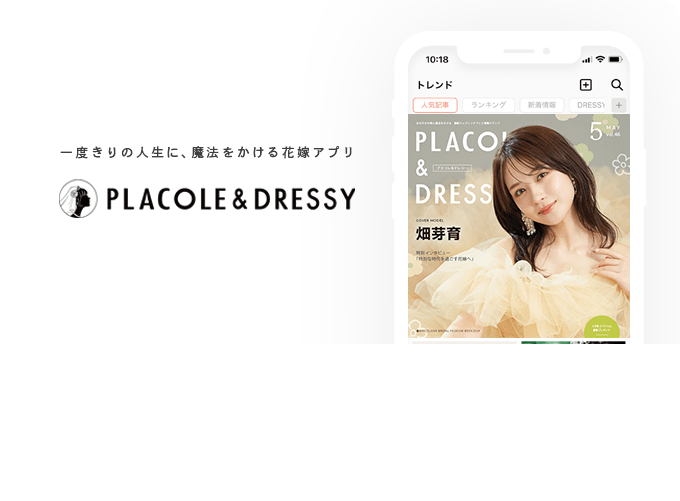先負の由来と歴史

どうしても「縁起が悪い」というイメージが先行しがちな先負。しかし、かつては吉日のひとつだったことをご存知でしょうか?ここでは、六曜における先負の由来と歴史について詳しくご紹介します。
先負の名前の由来とは?
冒頭でもお伝えした通り、先負という名前の由来は「先んずれば負ける」という意味にあります。と言いますのも、六曜自体がもともと賭け事の日取りを決めるために使われていたとも言われており、先負は特にその要素が色濃く残る日なのです。
つまり本来の先負とは「相手より先に勝負を仕掛けると負ける」という意味にすぎませんでした。慎ましく行動すればむしろ吉日とされていたのです。しかし、時代とともに先負が小吉・周吉といった漢字表記に転じたことで、午前は凶とされるようなりました。そして最終的には現代の解釈「午前は凶・午後は吉」に繋がったと言われています。
先負の誕生と広がりを解説
他の六曜と同様に中国で誕生した先負。日本には鎌倉・室町時代に小吉という名称で伝来しました。これが江戸時代中期には周吉へと変わり、同じく江戸時代の後期には現在の先負に変化し、一般的に広く使われるようになりました。
また、江戸時代後期に庶民の間で広がってからは、運勢占いのひとつとして六曜が使われていたそうです。現代とはまた違った使い方ではあるものの「吉凶を判断するために活用されていた」という点においては、昔も今も変わらないことが分かりますね。
先負の⽇に適した⾏動と避けるべき⾏動とは?