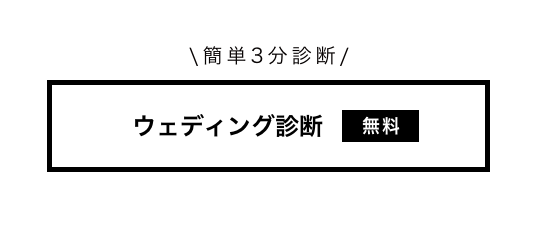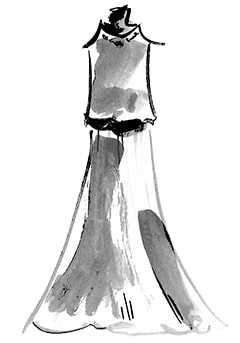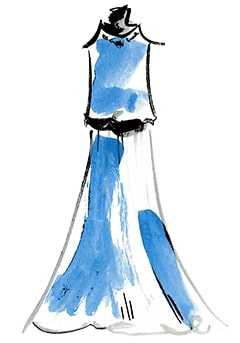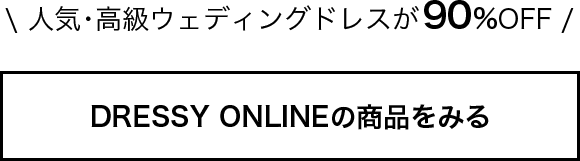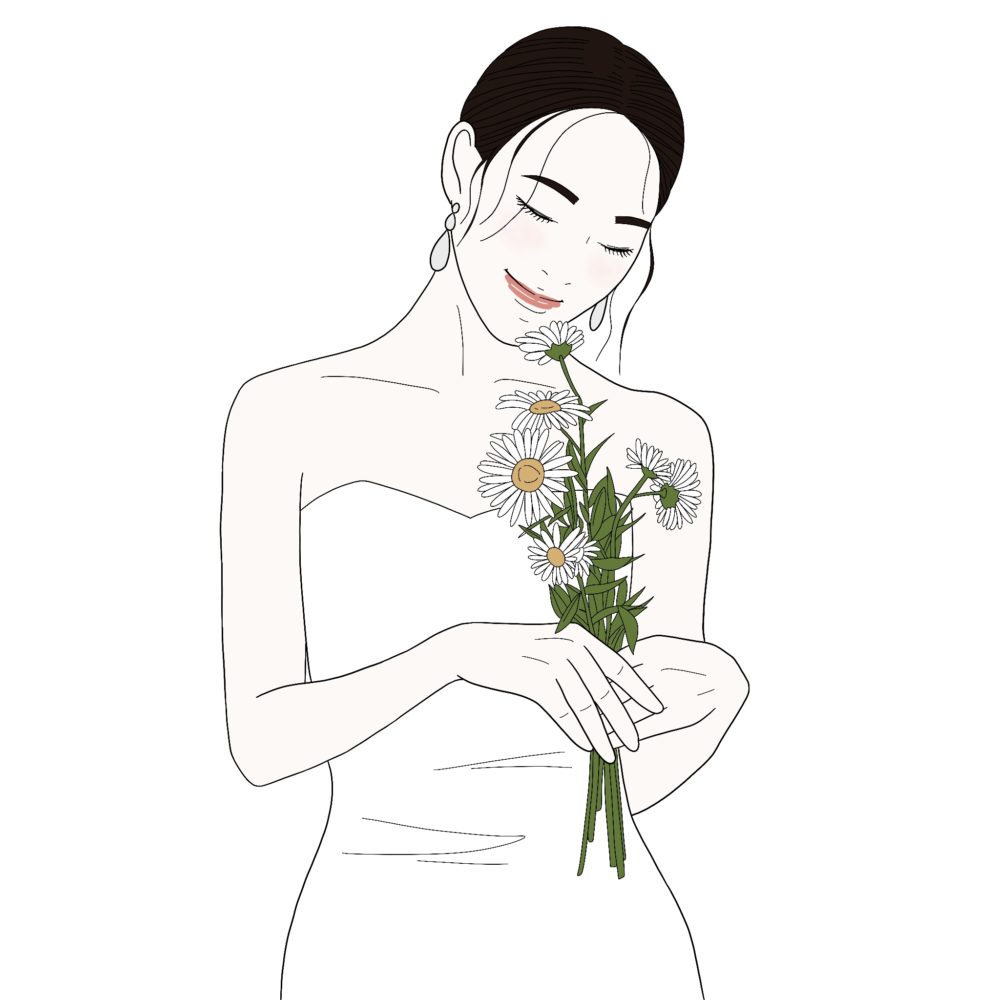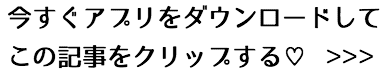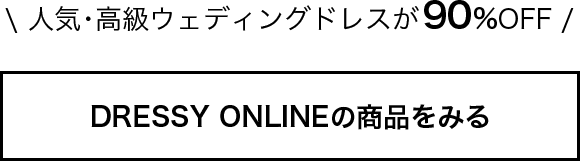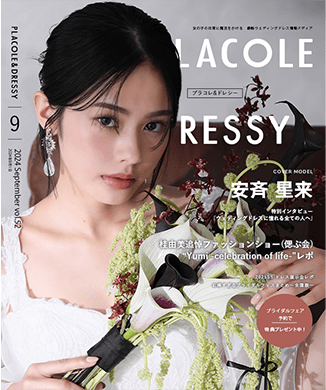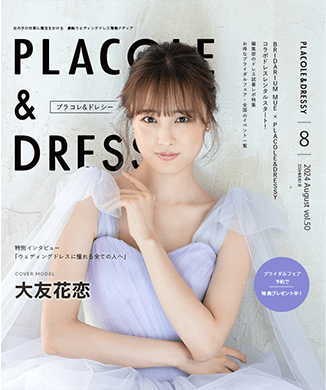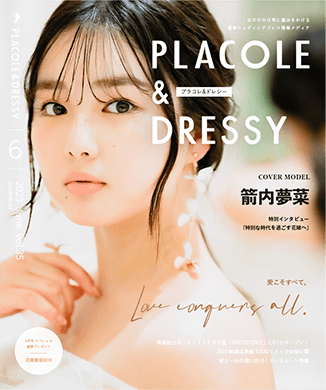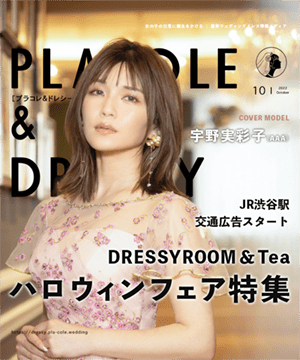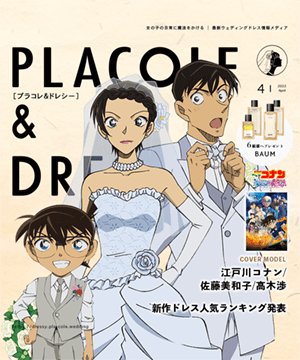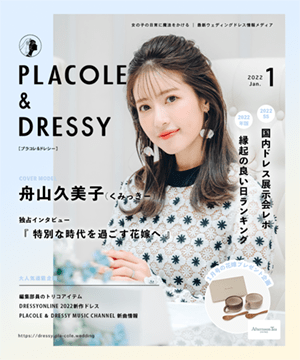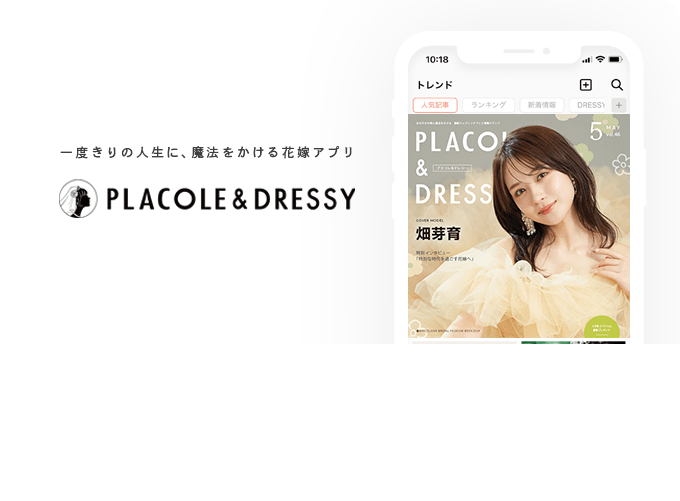秋田弁の特徴は?

「秋田ふるさと検定」を運営する
秋田商工会議所によると、
秋田弁と一口に言っても
鹿角方言、県北方言、中央方言、
県南方言、由利方言の5つの地域で
分けられているそう◎
そのため同じ秋田県内の人同士でも、
会話が通じないことがあります。
そして、秋田の方言の特徴は、
大きく分けて3つあります。
濁点が多い

秋田弁は言葉に濁点がつくことが非常に多いです。
例えば、「か行」と「た行」には
非常に高い可能性で濁点が付きます。
地方に住む高齢者の方は濁点に加えて
早口で大声で話すため、
知らない人が聞くと
怒っているように聞こえることもあるそう。
しかし、会話を聞いていると濁点だらけで、
何となく面白い気がしてきます。
イントネーションが面白い
秋田弁は文字で見るよりも、
実際に聞くとより面白い言葉だと感じます。
例えて表現すると、
3文字の単語を発音する時に
2文字目の音を高く発音するなどです。
また、母音の発音も特徴的で
「し」と「す」、「い」と「え」、「ち」と「つ」
などは秋田弁でほぼ同じ発音で話されているため
区別がとても難しいです。
そのため、県外の人が聞くと
「寿司(すし)」「獅子(しし)」「煤(すす)」
は全部同じ言葉を話しているように
聞こえてしまうんだとか*
イントネーションや発音の違いは
文字だけでは表現できないため、
ぜひ実際に秋田でリアルな秋田弁を
聞いてみてください♡
単語や言葉が短縮されている
言葉が短縮されるのは秋田だけではなく、
東北の近隣県の多くに共通している
方言の特徴でもあります。
これは豪雪地帯で冬場の寒い時に、
雪や吹雪の中でも、あまり口を開けずに
会話ができるように言葉が短縮されたんだそう◎
秋田弁を聞くと外国の言葉みたいで、
何を話しているか全くわからない…
と最初は思うかも知れませんが、
基本的な単語は
そんなに標準語と変わりがないと思います。
助詞や助動詞、イントネーションが
耳慣れないため違和感がありますが、
慣れてくると意味も分かり可愛らしく感じます♡
“ね”だけで会話が成立する!?
先程秋田弁の特徴でも話しましたが、
秋田弁では言葉が短縮され
話されることがしばしばあります。
代表的なのが、
“ね”だけで会話が成立してしまうというもの!
「ねねばねのにねれねねー」
これはどんな意味か分かりますか?
まるで呪文のように聞こえますが
ちゃんとした文章を話しているんです。
直訳すると
「寝なければならないのに寝れないね」
と言っています◎
“ね”という1文字に秋田弁では
『寝る』、『〜しなくてはならない』、
『〜しない』の3つの意味がある上、
標準語と同じ『〜ですよね』の意味で
語尾に『ね』が加わって
こんな文章が生まれてしまいました。
「食べれ」「来い」「かゆい」は全部”け”!?