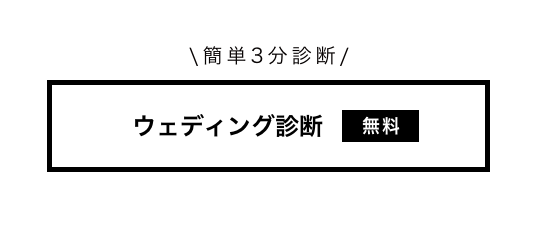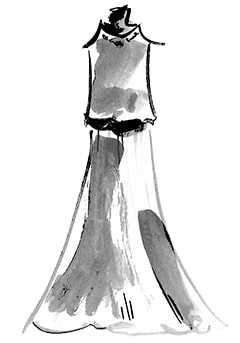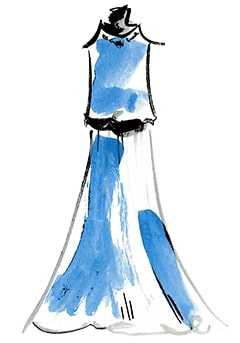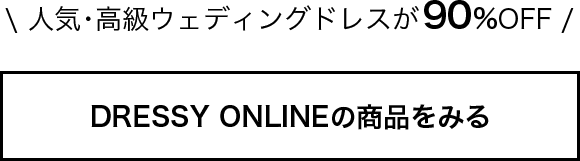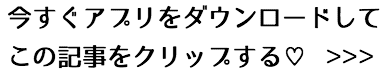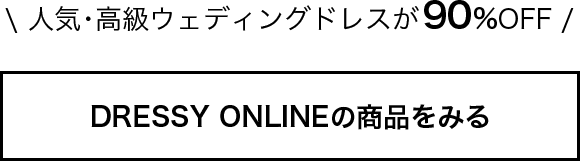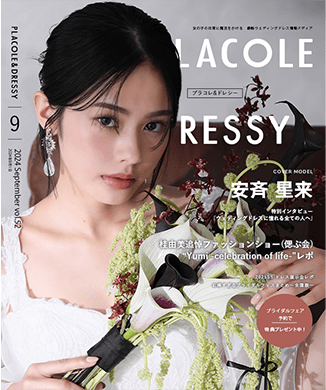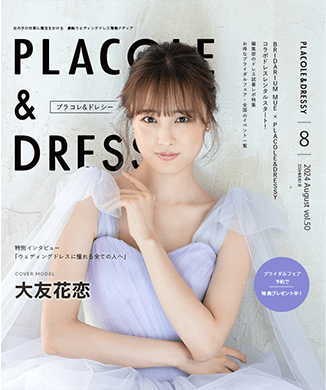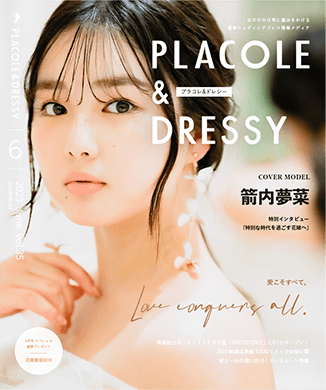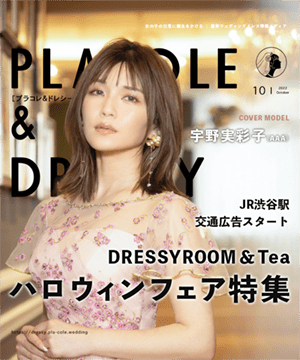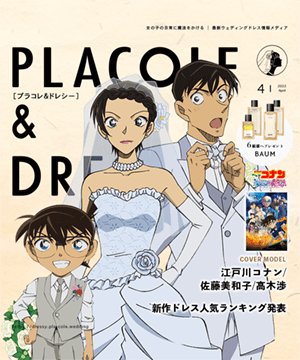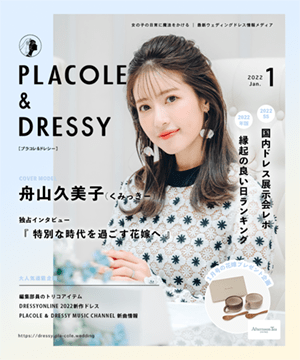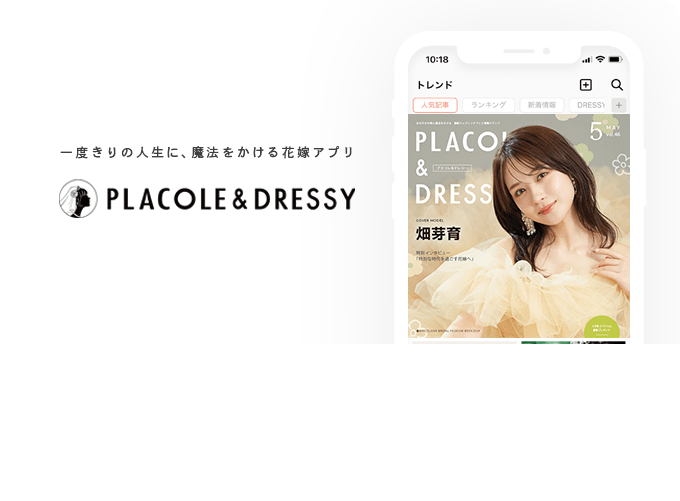助成金・補助金を申請する前に知っておきたい注意点
結婚・出産・育児に関する助成金や補助金は、家計の負担を軽減してくれる心強い制度ですが、申請前にいくつか注意しておきたいポイントがあります。
多くの制度で申請期限が短く設定されている点には注意が必要です。
婚姻日や出産日、妊娠届出日から「◯日以内」「◯か月以内」と期限が決まっているケースが多く、期限を過ぎてしまうと受給できなくなる場合もあります。
また、申請先は原則として住民票のある自治体となります。
結婚や出産を機に引っ越しをした場合でも、どの時点でどの自治体に住民票があるかによって、申請先や対象制度が変わることがあります。
里帰り出産をした場合でも、申請先は出産した病院の所在地ではなく、住民票のある自治体になるのが一般的です。
「出産した場所=申請先」と勘違いしやすいため、事前に確認しておくと安心でしょう。
さらに、助成金や補助金制度は年度途中で内容が変更されたり、予算上限に達すると受付が終了したりする場合があります。
前年と同じ内容とは限らないため、申請前には必ず最新情報を公式サイトで確認することが大切です。
制度を上手に活用するためには、「妊娠が分かった時」「結婚が決まった時」など、ライフイベントの早い段階で情報収集を始めることがポイントですよ◎
まとめ|助成金・補助金を上手に活用しよう

出典元:photoAC
今回は、結婚・出産・育児に関する助成金・補助金制度や、子育て支援事業についてご紹介しました。
これらの制度は、国が全国共通で実施しているものと、千葉県や市町村が独自に行っているものがあり、内容や条件、助成額は自治体ごとに大きく異なります。
今回ご紹介した自治体以外にも、地域の特性や子育て支援方針にあわせた制度が用意されているケースは少なくありません。
そのため、結婚や妊娠、出産をきっかけに、一度お住まいの自治体の公式ホームページをチェックしてみることをおすすめします。
助成金や補助金を知っているかどうかで、結婚生活や子育てのスタート時の負担は大きく変わります。
使える制度を上手に取り入れながら、無理のないライフプランを描いていきましょう!
この記事が、これから結婚や出産を迎えるみなさんの参考になればうれしいです♡
結婚新生活支援事業は、結婚に伴う新生活のスタートにかかる費用を支援するための制度です。
詳しい全国共通制度については結婚に関する補助金の全国版まとめも参考にしてみてください。
【全国版 結婚に関する補助金】結婚・出産・新居に引っ越すタイミングで活用したい! 転勤にも役立つ”全国版”補助金・助成金制度まとめ